こんにちは、頑張るパパママの幸せな子育てライフを勝手に応援する人、パパ三昧です。
今回は、パパ三昧が実際に1年間の育児休業を取得してみて感じた、育休取得のメリット・デメリットについてお話していきます。
記事後半では育休取得のデメリットに対する予防、対処法も紹介しています!
パパが育休を取得する際の参考にしていただければ幸いです!
男性育休の現状
男性の育休取得に対する注目度は年々高まってきています。
2017年度の時点で「子どもが生まれたら育休を取得したい」と希望している男性社員は79.5%と過去最高値を記録しています。(出典:日本生産性本部「2017年度 新入社員 秋の意識調査」)
しかし、実際のところ男性の育休取得率は2020年時点で7%台にとどまっているのが現実です。
この数字を見ると、多くのパパたちが、悩みに悩んだ末に育休取得を諦めている現状がうかがえます。
ここでは、そんな悩めるパパたちの参考としていただくべく、育休取得のメリット・デメリットについて見ていきます。
男性の育休、メリット・デメリット
【メリット】
- 子どもの成長を間近で見れる
- ママの負担を軽減できる
- 家事・育児への理解が深まる
- 夫婦や自分の時間を持てる
子どもの成長を間近で見れる
育児休暇を取得することで、自然と子どもと接する時間も増えます。
一緒に遊んだり、おむつを替えてあげたり、寝かしつけをしたり。
こういった何気ない日常の中で、子どもは目まぐるしく成長していきます。
寝返り、おすわり、つかまり立ちなどなど、子どもはできる事をどんどん増やしていきます。
その1つひとつをママと一緒にリアルタイムで発見・共有できる事は、パパにとって、何より家族にとって、この上ない喜びです。
ママの家事育児の負担を軽減できる。
これこそ、パパ育休一番のメリットではないでしょうか。
家事・育児でパパにできないことと言えば、妊娠出産と母乳による授乳くらいです。他のことは、程度の差こそあれ、やろうと思えばパパにもできます!
育休中はパパが日中も家で家事や子どものお世話ができるため、ママにも体力と心の余裕が生まれます。
出産直後のママは、寝不足、疲労、ホルモンバランスの変化で特にイライラしたり落ち込んだりしやすい状態にあります。
悲しいことに、出産後家事育児の大変さと孤独から鬱を発症し、中には自殺に追い込まれてしまうママもいるのが現実です。
そんな時に、パパが家族に寄り添い、家事・育児を率先して行うことで、ママの休息時間や自由時間を確保することができます。
子どもの成長にとって、最も重要な要素の一つは穏やかな家庭環境だと言われています。
ママの心と体の安定は、子どもの健やかな成長、ひいては家庭の幸せにも繋がります。
家事・育児への理解が深まる
多くの男性が思っている以上に、連日の家事・育児はハードです。
例えば、掃除、洗濯、買い物、食事の準備といった家事。これらは、一見大したことないように感じる方もいるかもしれません。
しかし、それぞれの家事には複数の行程があり、効率よくこなしていくのは意外と大変です。
さらに寝不足の状態で子どものお世話をしながら家事をこなすとなると、もう息つく暇もなく、意識も朦朧。加えて姉妹兄弟がいるものなら、もう朝から晩までてんてこ舞い。本当にしんどいんです。
パパは育休を通して、この家事・育児の大変さを肌で感じることができます。自然とママに対する労いや感謝の言葉が出てくるようになります。
また、この期間は自身の家事・育児スキルを高める絶好の機会でもあります。積極的に家事・育児ついて学び、取り組むことで、ママから感謝されることも増え、夫婦間の信頼関係も深まります。
夫婦や自分の時間を持てる
仕事が忙しい中、家事・育児をこなしていると、どうしても夫婦の時間や自分の時間が二の次、三の次になってしまいがちです。
パパが育休を取得することで、ママだけでなく、夫婦・パパの時間も確保しやすくなります!
例えば、子どもの寝かしつけ。ママが寝かしつけを担当し、その間にパパが家事を進めることができれば、お互い余った時間を自由に使えます。
読書や勉強をしたり、副業に挑戦してみても良いかもしれません。
また、時間に余裕ができることで、夫婦で育児のことや、家族の将来のことについて話す機会も増えます。
育児の方針や、家庭のルールをこの機会にゆっくり話し合うこともできます。
【デメリット】
- 一時的に収入が減る
- 職場への負担増加
- パタハラへの危惧
一時的に収入が減る
育児休業中は基本的に会社からの給料はもらえません。その代わり、雇用保険から育児休業給付金なるものが給付されます。(公務員の場合は共済組合から育児休業手当金が支給されます。)
給付の内容としては、育休開始から6ヶ月間は育休取得前の給与の67%、6ヶ月経過後は子どもが1歳になる日(誕生日の前日)まで50%の給付となります。
また、育休取得中は社会保険料の支払いが免除。さらに、育休中は無給のため所得税もかかりません。加えて育児休業給付金も非課税扱いですから、実際手元に入るお金は、最大で育休取得前の手取りの約80%程度になります。
手取りの約80%。あなたはどう感じますか?家庭によって約20%の収入減が家計に与える影響は異なりますが、一時的に収入が減少してしまうのは確かです。
職場への負担増加
育児休業を取得することによって、職場の同僚や上司、部下への負担増加が予想されます。
育休を取ることで生じる負担の例としては、次のようなことが考えられます。
- ・引継ぎの負担
- ・業務量増加の負担
- ・代替職員の手配にかかる負担
- ・育休取得前後の手続きにかかる負担
以上のような負担から、育休取得を良しとしない方々がいるのも事実です。最悪の場合、次にお伝えするような、パタハラにつながってしまうことも予想されます。
パタハラへの危惧
パタハラとは、パタニティハラスメントの略語で、男性が育児に関わることに対する不当な嫌がらせのことを言います。
パタハラの例としては、育休取得に対して職場で嫌味を言われたり、育休取得後に不当な人事異動を言い渡されるといった例があります。
近年、男性の育児休暇取得への注目度が高まってきてはいるものの、今だに男性の育休取得をよく思わない方々もいるのが現実です。
育児休業取得の前後に、そういった方々からパタハラを受けてしまう可能性があります。
デメリットに対する予防・対処法
一時的な収入減について
家計の見直し
収入が減るにも関わらず、以前と変わらない生活をしていると、収入と支出のバランスが崩れ、家計がどんどん苦しくなってしまう可能性があります。
そうならないためにも、無理のない範囲で支出を見直していく必要があります。
支出見直しのポイントは、ズバリ固定費です!
固定費の例としては、光熱費、通信料、保険料、サブスクリプションサービス、習い事、定期購入品などがあります。
ここで言う固定費の節約は、電気をこまめに消したり、水の使用を制限したりといったことではなく、現在加入済みのサービスやプラン自体を見直していくことを指します。
そういった固定費を削減することで、無理なく節約を継続することができます。というのも、毎月自動で支払っていた費用が、毎月自動で節約されることになるからです。また、食費や趣味にかかる費用の節約に比べ、負担感も小さく済みます。
固定費を見直す際の基準としては、2つ。「より安く、お得に活用できるプラン、サービスはないか。」「自分たちの生活にとって本当に必要なサービス(もの)か。」です。
例えば光熱費。特に電気代、ガス代については供給会社によって価格が異なったり、ポイント付与等のサービスを行っている等様々です。今より安くお得に使えるサービスへの切り替えを検討しみてはいかがでしょうか?
他にも、定期購入品やサブスクリプションサービスを購入している方は、今一度現在の生活、今後の人生にとって本当に必要なのかどうか見直してみるのも一つの手です。
副業に取り組んでみる
半年、1年と比較的長く育休を取得するのであれば家事育児の合間に副業に挑戦してみることで、収入の減少を抑えることも可能です。
ただし、育休中の副業について注意点が2つあります。
1つ目は副業をして良いかは職場次第だという点です。
基本的に育休中の副業も認められていますが、中にはそもそも副業を禁止していたり、育休中の副業を禁止している会社もあります。副業を検討している方は、後々のトラブルを防ぐためにも、事前に会社の規則等を確認しておくことをオススメします。
2つ目は稼ぎ過ぎると逆に損をする可能性がある点です。
というのも、育児休業給付金の給付要件には、「休業中に受け取る賃金が通常の8割を超えないこと」「就業日数が10日を超えない、10日を超えるときには、80時間以下であること」があるからです。
これらの要件を満たしていない場合には、給付金の支給に影響が出てしまいます。
副業をする場合には、お給料と働く時間の上限には十分注意する必要があります。
職場への負担増
職場への報告は早めに!
ママの妊娠が発覚し、育休取得の意思が固まったら、なるべく早く職場に育休取得について打診することが大事になります。できれば、ママが妊娠安定期に入る妊娠3ヶ月前後(※個人差あり)には職場に伝えたいところです。
というのも、あなたが育休を取得する場合、それに付随して様々な追加業務が発生するからです。また、人によっては、業務の引き継ぎ資料を作成する必要もあります。
そういった追加業務に余裕を持って取り組むことが出来るよう配慮することができれば、職場からの不満の声も上がりにくくなります。
引継ぎをしっかり行う
業務の引継ぎも職場への負担軽減の重要なポイントとなります。引継ぎを適当にしてしまうと、後任者が業務に躓きやすくなり、そのカバーのために上司や同僚の時間が取られるなど、職場の負担感が大きくなってしまいます。場合によっては、育休中あなたに職場から何度も業務に関する相談の連絡がくることにもなりかねません。
職場に迷惑をかけず、安心して育休に入るためにも、引継ぎは丁寧に行ないましょう。
業務引き継ぎのポイントとしては、4つあります。
- 1 業務の断捨離、効率化
- 2 業務スケジュールの作成
- 3 各業務のマニュアル作成
- 4 早めに引き継ぐ
業務の断捨離、効率化
育休の取得期間にもよりますが、必ずしも自分が今持っている全ての業務をそのまま引き継ぐ必要はありません。育休の取得が決まったら、自分の業務を一度棚卸ししてみて、不要な業務、より効率化できる業務を洗い出します。その上で、上司に引継ぐ業務について相談します。そうすることで、後任者の負担が減るだけでなく、組織としての生産性も上がりやすくなります。
業務スケジュール作成
引継ぐ業務が決まったら、次にそれらの業務を育休期間中に後任者がどのようなスケジュールでこなしていくのか考え、表形式でまとめていきます。そうすることで、後任者が引継いだ業務をスムーズにこなしていきやすくなります。
各業務のマニュアル作成
必要に応じて各業務の手順や注意事項を記したマニュアルを作成しておくことも、後任者の負担軽減に繋がります。業務の内容にもよりますが、マニュアルに必要な項目としては、業務の目的、進捗状況、業務に必要な知識、作業手順、各作業における注意事項、困ったときの相談先等があります。
早めに引き継ぐ
引継ぎは遅くても育休開始の1週間前には終えるようにしましょう。後任者が業務スケジュールやマニュアルを確認し、疑問点などがあれば、育休開始前に解決する時間を確保するためです。そのためにも、育休の取得が決まったら、すぐにでも引継ぎの準備に取りかかりましょう。
以上のように、引継ぎを素早く丁寧に行うことで、職場への負担を最小限に抑えることができます。
普段から職場での信頼関係を築いておく
心理学の言葉に返報性という言葉があります。これは、相手から何か親切にされたり、手伝ってもらった際に、お返しに何かしてあげたくなってしまう、人間の性質を表す言葉です。
きっと、あなたもそのような経験があるのではないでしょうか?
これは育休取得に限った事ではないですが、普段から雑務を積極的に引き受けたり、上司や同僚、部下が困っているときには進んで協力するなど、職場での信頼関係をしっかり築いておくことも大切なポイントです。
※自分の業務が疎かになっていない事が大大大前提です。
もちろん、返報性などは意識せず、自然に人助けができるのが理想ではありますが、職場で育休取得を言い出しづらいと感じているのであれば、返報性を意識してみるのも良いかもしれません。
職場での信頼関係があるのと無いのとでは、育休取得を打診したときの相手の反応が全く変わったものになるはずです。
罪悪感を感謝に切り替える
またまた心理学の話になってしまうのですが、同じ場面でも「すみません」と「ありがとう」では相手に与える印象がまるで変わってくると言われています。
例えば、あなたの育休取得のために尽力してれた上司対し、あなたなら「お忙しい中、すみませんでした。」「お忙しい中、ありがとうございました。」どちらを使いますか?
一見、前者の方が謙虚で良さそうですが、実は、心理学的には後者の方が、相手に与える印象が良い言われています。
というのも、「すみません」は自分に非があることを認める表現で、相手に「忙しい中、わざわざやってあげた」というマイナスの感情を引き起こす一方で、「ありがとう」は相手の徳を敬う表現であり、相手に「役に立てて良かった」というプラスの感情を引き起こすとされているからです。
もちろん、明らかに自分に非がある場合は、素直に「すみません」と謝る必要があります。
しかし、むやみに「すみません」を乱発していると、周りからお荷物扱いされてしまうことになりかねません。
育休を取得するにあたって、様々な人に感謝の気持ちを伝える場面が増えます。そういった場面で、「すみません」ではなく「ありがとう」を使うことで、あなたが育休を取得することに対する印象をより良くすることができます。
さらに、「ありがとう」は使った本人の心も前向きにしてくれます。罪悪感の中で育休ライフを送るよりも、感謝の気持ちを持って生活していたほうが、精神的にも安定します。
パタハラについて
パタハラの予防については、②職場への負担増と共通しています。というのも、パタハラの発生原因の1つは、育休取得によって職場への負担が増加にあるからです。職場への負担を最小限に抑えることは、パタハラの予防にも繋がります。
しかし、どんなに職場への負担を軽減できるよう考慮したとしても、パタハラが絶対に起こらないとは言い切れません。というのも、日本社会には今だに「男は外(仕事)、女は内(家庭)」という固定観念を持った方が一定数いるからです。そういう方々からすると、男性の育休取得は納得がいかず、取得者に対するパタハラに繋がる可能性があるからす。
そこで、万が一パタハラを受けてしまった場合、次のような対処法があります。
- 1 職場や社外の育休取得経験者に相談する
- 2 職場の人事部や社外機関に相談する
職場や社外の育休取得経験者に相談する
大前提として、パタハラを受けたことによる悩みは一人で抱え込まないことが大切です。職場や社外に育休取得経験のある知り合いがいれば、まずはそういった方に相談してみることをおすすめします。相手が経験者であれば、悩みに対する共感や解決のための協力を得られる可能性が高いからです。
職場の人事部や社外機関に相談する。
周りに相談できるような人がいない場合、職場の人事部など育児休業申請等を担当する部署に相談してみるという方法もあります。また、組織的なパタハラに悩んでいる場合には、社外機関の相談窓口を利用することをおすすめします。相談窓口の例としては、育児休業法に関する相談に応じる雇用均等室等があります。
実際にパタハラを受けてしまった場合には、絶対に一人で抱え込まず、経験者、できれば専門家のアドバイスをもとに適切な対処をとるようにしましょう。
まとめ
今回は、パパが育休を取得することのメリット・デメリット、そしてデメリットに対する予防・対処法について見てきました。
育休を検討しているパパママの心の底にあるのは、「家族を幸せにしたい」という想いではないでしょうか?
パパの育休取得には、家族を幸せにする様々なメリットがあります。
確かに育休は周りの協力なくして取得できるものでありません。デメリットで挙げたようなパタハラを受けてしまうリスクもあります。しかし、普段から職場でより良い人間関係を築き、段取り良く育休申請手続きを進めていけば、そういったリスクも最小限に抑えることも可能です。
また、万が一パタハラの被害にあった場合、一人で抱え込まず、育休経験者や専門家の協力を得ることで、解決の糸口を見出すこともできます。
私たちの長い人生において、仕事は一生、育児は一瞬です。どちらも大切ですが、あなたなら今優先すべきはどちらだと考えますか?
本記事があなたの育休取得検討の参考となれば幸いです。それでは、また別の記事でお会いしましょう!
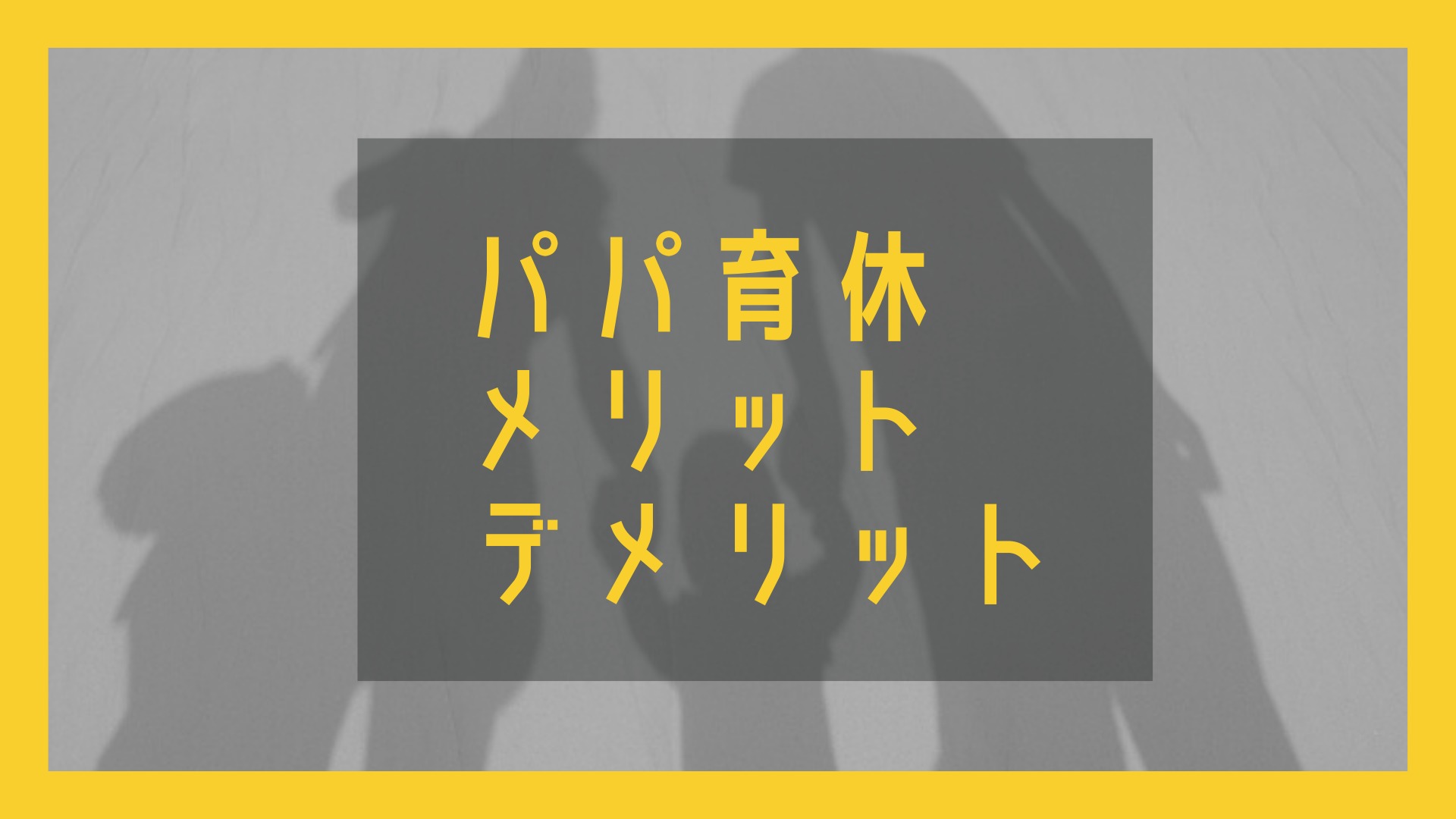

コメント