こんにちは、頑張るパパママの幸せな育児ライフを勝手に応援する人、パパ三昧です。
2020年1月に、主婦に特化した人材サービス「しゅふJOB」の調査機関「しゅふJOB総研」が、働く主婦層644人に行ったアンケート調査によると、過半数の52.5%の人が夫の家事・育児協力に関して「不満」を持っていることが分かりました。

せっかく家事育児に協力しているのに、不満をもたれてるなんて、なんだか不本意だなあ。
そんな風に考えるパパも少なくないと思います。では、ママ達はパパの家事育児のどんなところに不満があるのでしょう。
パパの家事育児の質の低さ、家事育児負担の不公平感など、原因はさまざまあります。
そして、それら原因の根本には「多くのパパが家事育児の本当の大変さを理解していない」という現状があるのではないでしょうか。
パパとママで家事育児に対する考え方にすれ違いがあると、その後の夫婦生活にも影響を及ぼしかねません。
家事育児の大変さをしっかり理解しているのといないのとでは、パパの家事育児への姿勢やママへの声がけなんかも変わってきます。
そこで今回の記事では、パパ三昧が1年間の育休で体感した家事育児の大変さを、職場での仕事に置換えながらご紹介していきます。
今回の記事は、以下のようなパパたちの参考になればと思い、書きました。
- 普段から家事育児に積極的に関わっているつもりなのに、ママに認めてもらえず、やる気をなくしてしまいそうなパパ
- そもそも家事育児はママの仕事だと考えてるパパ
- 家事育児に関わりたいとは思うが、何をしたら良いか分からないパパ
また、この記事を読むことのメリットは次の3つです。
- 家事育児の大変さが理解できる
- ママへの感謝、労いの気持ちが増す
- ママから感謝される家事育児ができるようになる
それでは、早速見ていきましょう!
家事育児の特性
まず、家事育児(幼児期)には次のような特性があります。
- やることがやたらと多い
- 制限時間、拘束時間にがんじがらめ
- 相手は言葉が通じない
- 不測の事態が連発する
- 命を預かっている
- 年中無給(休)
やることがやたらと多い
家事育児はとにかく細々としたタスクをたくさん含んでいます。育休取得中にママ三昧と協力して、家事育児をリストに書き出してみたところ、その数148。そのうち、毎日必ずこなすべきタスクは56ありました。
中には、「洗濯前にポケットの中確認」、「衣類は大人用と子供用分けて洗濯」、「子どもの爪の長さ管理」など、恥ずかしながら、育休を取得するまで存在自体気づいていなかった家事育児もいくつかありました!笑
制限時間と拘束時間にがんじがらめ
家事育児は制限時間との戦いでもあります。毎日おおよそ決まった時間に発生するタスクがあり、また、そのタスクを開始するまでに済ませておかないといけないタスクも存在します。
例えば寝かしつけ。我が家の弟三昧(10ヶ月頃)の場合、午前10時、午後3時、午後9時が寝かしつけの時間。朝起きてから、朝10時の寝かしつけ前に済ませるタスクは、
授乳1回、おむつ替え、娘三昧の着替え、水筒に水を入れる、朝食準備、朝食食べさせる、朝食の片付け、前日夜に回した洗濯物を干す、子どもたちの遊び相手、お散歩、第2回おむつ替え、おやつの準備、おやつを食べさせる、昼飯の下準備
といった感じで盛りだくさん。
また、授乳や寝かしつけをしている間は、一定時間他のタスクを平行して行うことが難しく、家事育児における、拘束時間であるともいえます。
このように、家事育児にはいくつか制限時間つきタスクがあり、制限時間内に終わらせていないと、子どもが泣き出す、なかなか寝てくれない、家事が滞るなどの二次災害が発生することとなります。
相手は言葉が通じない
育児の相手は赤ちゃん。もちろん言葉は通じません。
生後数ヶ月間は話しかけても応答がない時期が続きます。しかし、気持ち悪い、お腹すいた、眠い、嫌だなど、本能的な意思は持っているようです。
赤ちゃんはそんな時、泣くことによってこちらに思いを伝えてくれます。ですから、パパママは赤ちゃんの思いを汲み取ってお世話をしていくことになります。
時には何をしても泣き止まず、ただひたすら抱き続けることしかできないこともあります。
不測の事態が連発する
舐める、食べる、触る、投げる、引っ張る、などなど、赤ちゃんにとってこういった基本動作は楽しくて仕方ありません。自制心と物事の分別のがまだない赤ちゃんは、ちょっと目を放した隙に、とにかく色々やらかしてくれます。
部屋が散らかるくらいならなんともないですが、誤飲誤食、火傷や、頭ごっちん、ベットから落下などなど、命に関わるようなリスクがたくさんあります。
もちろんこれらのリスクはある程度予防できますが、それでも好奇心旺盛な赤ちゃんはパパママの予想を軽々と超えてきます。育児をしていると、一日に何度もヒヤッとする場面に遭遇します。
命を預かっている
上でも見たように、家事育児、特に育児をするパパママには、子どもの成長サポートと平行して、子どもの命を守る責任があります。
育児の最中にもしものことがあったら、取り返しがつきませんし、悔やんでも悔やみきれないことになってしまいます。
年中無給(休)
これだけ責任重大で、ハードな育児ですが、基本的には無給です。育児休業取得中のパパママであれば、働いていた頃の数十パーセントの給付金を受け取ることができますが、これは家事育児に対して支払われるものではないです。副業による収入も同じです。
また家事育児に休暇は基本的にありません。子どもがある程度成長するまで365日24時間の対応が必要となります。
家事育児を職場の仕事に置き換えてみる
家事育児には、上で見たような6つの特質がありました。では、その6つの特質を仕事に当てはめてみると、どんな感じになるでしょう。
やることがやたら多い仕事
これについては、さまざまな仕事に当てはまることなので、説明は割愛します。笑
制限時間と拘束時間にがんじがらめな仕事
これはたとえて言うなら、毎日一日に何度も会議が入ってくるような仕事です。
会議を行うためには、会場準備、資料準備、出席者調整、などなど様々な雑務がついてきますよね。
また、会議の最中はその他の仕事を進めることが難しいので、業務が滞ってしまいます。
相手と言葉が通じない仕事
これを仕事にたとえるなら、田舎の小さな温泉旅館に突然日本語ができない外国人のお客さんが来たような感じですかね。
外国語ができる職員がいればいいですが、そうでない場合はかなり大変な状況になることが容易に想像できると思います。
ただ、この場合、今の時代は通訳翻訳アプリなどもあるので、何とかなるかもしれません。
でも、今のところ赤ちゃん語の翻訳アプリはないのが現状です。
不測の事態が連発する仕事
これは、多忙なコールセンターで働いているところ想像していただけると分かりやすいかと思います。
ひっきりなしに、苦情やお問い合わせの電話が鳴り響き、その対応に追われる感覚です。
命を預かる仕事
育児も子どもの命を預かっている以上、お医者さんや、消防士、警察官などと似たような責任を負っているといっても過言ではないでしょう。
年中無給(給)の仕事
ボランティア、又はサービス残業を毎日24時間していると考えると分かりやすいです。
つまり、家事育児を職場での仕事に置き換えると
「無数かつ責任重大なタスクを、会議の合間を縫って、頻発する不測の事態に対応しながら、年中無給(休)でこなしていく仕事」
ということになります。
どうでしょう。家事育児の大変さ、伝わりましたか?
もしあなたがこんな状態の職場に一人っきりだったらどうですか?
ママが喜ぶ家事育児のコツ
家事育児の大変さが理解できると、ママと協力して家事育児を進めていくためのパパが意識すべき3つのことが見えていきます。
- 言われる前にやる
- ついでにやる
- 楽しそうにやる
言われる前にやる
ママに何度も同じことを頼まれていませんか?
もしそうなら、「なんでいつも言われないとできないの?」とママの不満ゲージが上昇中かも知れません。
家事育児はやることが山ほどあります。パパに指示している時間も惜しいほど、バタバタしている時もあります。
それでもパパに何度もお願いしてくるということは、その家事はパパの担当にして欲しいと内心思っているかもしれません。
また、特に普段頼まれることのない家事でも、パパが率先してやることでママも助かります。そのためには、家事育児の見える化をお勧めします。
一度、ママとゲーム感覚で家事育児の項目をリストアップしてみると、パパにできることが見つかるはずです。
ついでにやる
何かをやるついでに家事を済ませるとママも「お!ありがたい!」ってなります。
例えば、歯磨きをするついでに洗面台の整理整頓をする。とか、
洗濯物を取り込むついでに、裏返っている服を元に戻す。とか、、、
こんな感じで、セットでできる家事が色々あります。
このことを意識して家事育児をしていると、ママの負担を格段に軽減することができます。
ここでも、家事育児リストが役に立ちます。家事育児を見える化することで、セットでできる家事を発見しやすくなります。
楽しそうにやる
家事育児は楽しんでやりましょう!
育児は楽しいけど、家事は正直面倒。。と思っているパパは結構多いと思います。
面倒だと思いながら家事をやっていると、やることが適当になってしまったり、態度や表情に出てしまいます。
そんなパパを見ていると、「何でちゃんとやってくれないの?」ママの不満ゲージはぐんぐん上がっていきます。
家事は工夫次第で、楽しくなります。
例えば子どもと一緒に家事をやると結構楽しめますよ。家事をしていると、子どもの方からやってみたそうに近づいてくることがあります。
そんな時は、「あっちで遊んで待っててね」言うのではなく、その子にできそうなことを手伝ってもらうといいと思います。
床の拭き掃除、洗濯を干したり、取り込んだり、掃除機のスイッチを押してもらったり。小さな子どもでもできることはたくさんあります。
わが子が一生懸命手伝ってくれる姿をみていると、自分もだんだん楽しくなってきますよ。
パパが楽しそうに家事育児に取り組んでいる姿を見れば、ママもきっと嬉しいはずです。
ママに心からの「ありがとう」と「お疲れ様」を言おう!
パパ三昧は実際にワンオペ育児を体験してみて初めて、家事育児の本当の大変さに気づきました。それ以来、ママに対して自然に「ありがとう」や「お疲れ様」という言葉を使う機会が増えました。
夫婦間で「ありがとう」、「お疲れ様」と声を掛け合うことが増えたことで、ママ三昧がイライラしている時間が格段に減りました。
感謝と労いの気持ちをお互い伝えあうことは、夫婦関係を良好に保つ上での、基本中の基本ですが、意外とできていなかったりします。
これを機に、日ごろのママへの声がけについて見直してみてはいかがでしょうか。
本記事が、ママからの不本意なイライラに悩まされているパパたちの、お悩み解決の参考となれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!また別の記事でお会いしましょう!
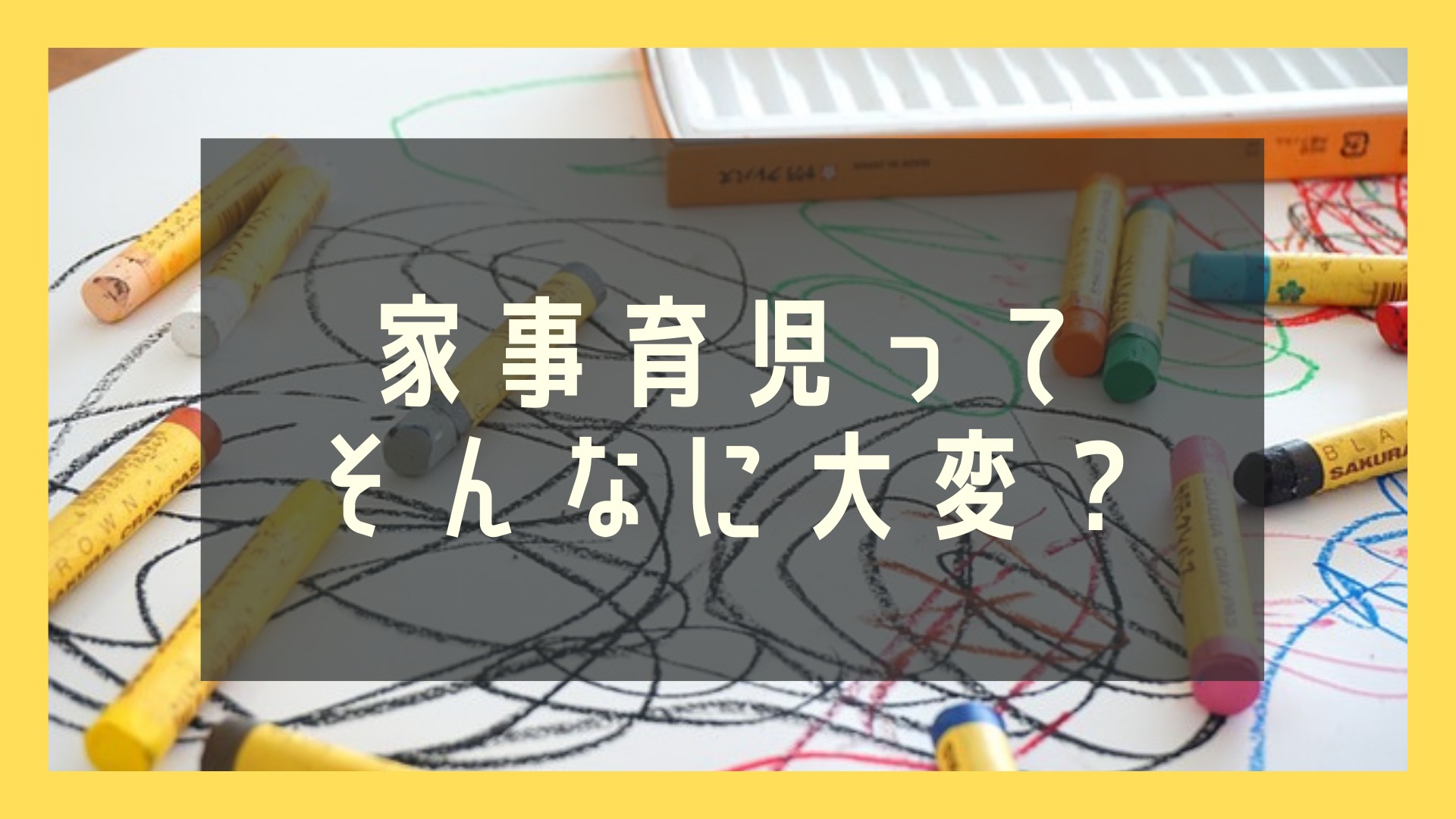


コメント